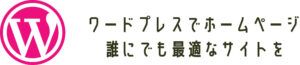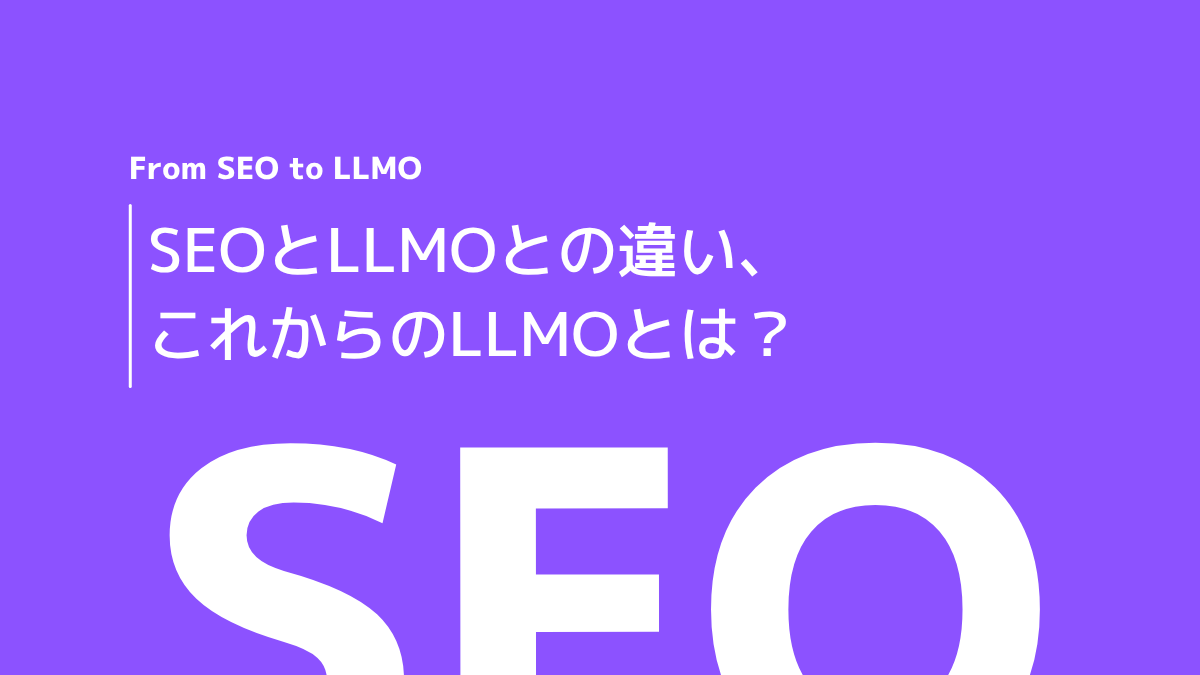Last Updated on 2025年10月22日 by ワードプレスの学校 学長 柳内郁文
近年、インターネット上での情報探索・発信のかたちは急速に変化しています。従来の「検索エンジン(たとえば Google Search/Bing 等)へのウェブサイト最適化=いわゆる SEO(Search Engine Optimization)」に加えて、生成系 AI や大規模言語モデル(LLM: Large Language Model)を考慮した新たな最適化手法が注目され始めています。そこでは「ウェブサイトがいかに AI に引用・参照されるか」「AI の回答エンジンに取り上げられるか」が可視性(visibility)のカギになることが増えてきています。これが「LLMO(Large Language Model Optimization)」と呼ばれる概念です。
本稿では、まず従来の SEO の基本とその限界を整理し、その上で LLMO が何を意味するか、SEO との違いは何かを明確にします。さらに、これからの時代において LLMO がどう進化し、どのような対応が求められるかを論じていきます。
従来の SEO とは何か
まず、SEO(Search Engine Optimization)について整理しましょう。SEO は、ウェブサイトやコンテンツを検索エンジンの結果ページ(SERP: Search Engine Results Page)で上位に表示させ、ユーザーを誘導してアクセスを増やし、最終的にはコンバージョン(問い合わせ、購入、資料請求など)に繋げることを目的にしています。
典型的には以下のような施策が伴います。
- キーワード選定:ユーザーが検索窓に入力する語句(キーワード)やフレーズを想定し、そのキーワードを適切にタイトル、本文、メタデータに含める。
- 内部施策(オンページ):見出し構造(H1, H2…)、本文の段落構成、読みやすさ、文字数、画像の alt 属性、内部リンク構成など。
- 外部施策(オフページ):被リンクの獲得、SNS/シェア/言及、ドメインの信頼性(ドメインオーソリティ)など。
- 技術的 SEO:サイト高速化、モバイル対応、構造化データ(Schema.org)実装、正規化 URL、XML サイトマップ/robots.txt 等。
- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の対応:特にコンテンツの専門性や権威性、ユーザー・検索エンジン双方にとって信頼できる情報であることを示す。
こうした施策を実践することにより、検索エンジンに「このページはユーザーが求めている情報を適切に提供しており、他より価値が高い」と判断してもらい、検索結果で上位表示を獲得し、ユーザー流入を増やすというのが SEO の基本構造です。
しかしながら、インターネット環境・検索行動・アルゴリズムの進化に伴い、従来の SEO だけでは対応しきれない変化が生じています。例えば、検索クエリが会話型になってきたり、生成 AI が「検索結果ページを経ずに直接答えを返す」動きが出てきたりしている点です。
なぜ「SEOだけでは足りなくなってきた」のか
SEO が重要であり続けるのは間違いありませんが、以下のような変化により、これまでのような「ただ上位表示させれば良い」という単純な構造では限界を迎えつつあります。
1. 「ゼロクリック」が増えている
例えば、検索結果上位に表示されたとしても、ユーザーがそのページにクリックせずに完結してしまう「ゼロクリック検索」の割合が増えています。特に AI による回答生成型検索(たとえば ChatGPT や Google Gemini 等)では、ユーザーがリンク先に遷移せず直接回答を得るケースがあります。
この流れでは「上位表示=クリック数増加」という公式が必ずしも成立しません。
2. 検索エンジンの変化と AI の介在
検索エンジン自身が、従来の「リスト形式でリンクを表示」というモデルから、「生成 AI が質問に対して直接回答を生成する」モデルへシフトしています。たとえば Google が「Search Generative Experience(SGE)」を導入していることもあり、AI を介した回答提供が進行しています。
この変化により、ユーザーは「キーワードを入力してリンクをたどる」よりも「質問を投げて即答を得る」流れに移行する可能性が増えています。
3. 大規模言語モデル(LLM)の登場・普及
Large Language Model(LLM)は、数十億〜数千億パラメータのニューラルネットワークを使って、自然言語の生成・理解を行います。
こうしたモデルは「文脈を理解して答える」「質問に対して要約して提示する」など、検索エンジンとは異なるインターフェースを用いた情報提供を可能にしています。このため、ウェブコンテンツも「ただキーワードを詰め込んで上位を狙う」だけでは、こうした AI に適切に理解・引用されることが難しくなっています。
こうした背景から、従来型の SEO 最適化だけでは「AI 経由で引用・推薦される」という新しい可視性軸に対応できなくなりつつあるのです。
LLMO(Large Language Model Optimization)とは何か
ここで改めて、「LLMO=大規模言語モデル最適化(Large Language Model Optimization)」という概念を整理します。これは簡単に言えば、「ウェブコンテンツを、LLM や生成 AI に“読まれ・参照され・引用されやすい”よう最適化する手法」です。
LLMO の定義・背景
「LLMO」という言葉自体は比較的新しく、厳密に定義された学術領域というよりも、マーケティング/コンテンツ戦略領域で用いられ始めた概念です。たとえば「LLMOとは?SEOとの違いと、AI時代を勝ち抜くための最新対策を …」という記事で、次のように説明されています。
「SEOがGoogleなどの検索エンジンアルゴリズムを対象に検索結果の上位表示を目指すのに対し、LLMOは大規模言語モデル(LLM)が情報を正確に理解・引用しやすいコンテンツ構造の構築を重視します。」
また、構造化データ・FAQ形式・文脈の明確化などが LLMO の重要要素として挙げられています。
LLMO の目的
従来の SEO が「検索結果ページで上位を取る」ことを目的としていたのに対して、LLMO の目的は少し異なります。以下のような観点が重要です:
- LLM や生成 AI の回答エンジンにおいて、自社/自分のコンテンツが「出典・参照ソース」「回答としてピックアップされる情報」として用いられること。
- ユーザーがリンクをクリックしなくとも、AI の回答中に名前が出たり、引用されたり、参照されたりすることで、ブランド認知・信頼を獲得すること。
- 「検索エンジンを通じた流入」だけでなく、「生成 AI を通じた流入・発見・認知拡大」という新しいチャネルを意識すること。
- コンテンツ構造を「AIが理解しやすい・要約しやすい」形で整えること。
例えば、記事中の Q&A(FAQ)形式、明確な見出し・段落構造、Schema.org 等による構造化データ、llms.txt のような AI 向けサイト構造の提示ファイルなどが活用され始めています。
SEO と LLMO の違い:具体比較
ここまで整理してきた SEO と LLMO の特徴を、もう少し具体に「違い」という視点から整理しましょう。以下は、先行記事にある比較表を元に私なりに整理したものです。
| 比較観点 | 従来の SEO | LLMO(LLM 最適化) |
|---|---|---|
| 主な対象 | 検索エンジン(Google/Bing など) | 大規模言語モデルや生成 AI の回答/参照エンジン |
| 主な目的 | 検索結果での上位表示 → ユーザー流入増加 | AI からの引用・参照・回答において「使われる/参照される」こと |
| 評価される要素 | キーワード最適化、被リンク、内部リンク、滞在時間など | 文脈の明確化、構造化データ、ブランドの一貫性、FAQ構造、正確で専門的な情報 |
| 成果の指標 | 検索順位、オーガニックトラフィック、CTR、滞在時間、離脱率など | AI に現れているか(引用・参照数)、AI からの流入、ブランド名が回答に含まれているか、AI 経由のコンバージョンなど |
| コンテンツの書き方 | キーワードを含め、リンク獲得・量産・スピード重視のケースも | 人間ユーザーにとって有用であると同時に、AI が「この情報を参照すべきだ」と理解できる構造・文体・信頼性を備える |
| 技術的な仕組み | XML サイトマップ、robots.txt、モバイル最適化、ページ速度、リンク構築など | 加えて:構造化データ(FAQPage, HowTo など)、llms.txt 等の AI 向け指示ファイル、ナレッジグラフ・実エンティティ (brand, person, organization) の明確化 |
このように、SEO と LLMO は「最適化の対象」「成果指標」「コンテンツの設計思想」において明確な違いがあります。ただし一方で、両者は「良質なコンテンツを提供する」「技術的に整備されたサイトを運営する」という点で重なっており、独立した完全な別物というよりも「SEO が進化・適応して LLMO を包含していく関係」と見る見方もあります。実際、Ahrefs のブログでは「GEO(Generative Engine Optimization)=LLMO は、SEO の一部として捉えられる」との見解が出ています。
なぜ今「LLMO」が重要なのか
では、なぜ今この LLMO が注目され、対応が急務とされているのでしょうか。主な理由として以下が挙げられます。
(1)ユーザー行動の変化
ユーザーの情報取得手段が変わってきています。従来「検索エンジンにキーワードを入れて、リンクをたどる」だったのが、最近では「生成 AI に質問して答えを得る」「チャット形式で探索する」というシーンが増えています。こうした変化は、リンクを辿らずとも回答を得られる「ゼロクリック」や「チャット型インタラクション」の台頭からも読み取れます。
この流れが加速する中で、「検索順位を上げるだけ」ではブランドが見えなくなる(AI が回答を生成したとき、自社サイトが参照されていない)リスクが高まっています。
(2)検索エンジンそのものの変化
検索エンジンが AI を内包し、「Lists of links(リンクの羅列)」型から「Answer + 少数リンク/参照」型へと変化しつつあります。たとえば Google が SGE を推進していること、AI が外部データを取得して生成回答を行うようになってきていることがそれを裏付けます。
そのため、従来の SEO のルールだけでは「AI にどう引用されるか」という観点が抜け落ちており、そこを補完する形で LLMO が重要になっているのです。
(3)ブランドや情報ソースとしての「参照される価値」の重要化
AI が答えを作るとき、どのウェブサイト/どのブランドを「信頼できるデータソースとして参照するか」を判断します。したがって、ただユーザー流入を増やすだけでなく、「AI に信頼され、参照される存在になる」ことが可視性戦略の新しい柱です。構造化データ、FAQ、ナレッジグラフ、社外の信頼チャネル(被引用・信頼されている外部サイトでの言及など)が、その信頼性を左右します。
(4)競争優位の転換
AI 参照枠の中で先行できるかどうかが、今後の競争優位になり得ます。たとえば自社が生成 AI の回答エンジンに参照されなければ、ユーザーがその AI を使った際に自社が選択肢にすら上がらない可能性があります。いわば「被リンク」が検索エンジン時代の価値だったとすれば、「AI による引用・参照」が AI 時代の価値になりつつあるとも言えます。
以上の理由により、SEO に加えて LLMO の視点を取り入れることが、デジタルマーケティング/コンテンツ戦略において重要になってきているのです。
具体的に「これからの LLMO」では何をすべきか
では、実務的に「これからの LLMO」で押さえておくべき点を整理します。少し先を見据えた視点も交えてお伝えします。
1. コンテンツ構造・文体を AI に理解されやすくする
- FAQ形式・Q&A形式の導入:生成 AI は質問・回答形式の構造を好む傾向があります。コンテンツ内に「Q. 〜?」「A. 〜。」といった明確な問いと答えを設けることで、AI が “このページは質問への回答集だ” と認識しやすくなります。
- 見出し・段落構造の整理:Hタグ(H1, H2, H3…)を論理的に使い、読みやすくスキャン可能な構造にしておくこと。AI が文章を要約・参照する際に構造が整っている方が扱いやすいです。
- 自然言語・文脈重視の執筆:単なるキーワード詰め込みではなく、「ユーザーが本当に知りたい問い」を自然な語りで回答する形を意識します。これは AI が「文脈を理解して意味を把握する」ことを前提としているためです。
2. 構造化データ・技術的整備を強化する
- Schema .org の実装:FAQPage、HowTo、Organization、Product、Review など、該当するスキーマを用いてコンテンツの意味を明確にマークアップします。AI はこうした構造化データを手がかりに「このページにはこういう意味・役割の情報がある」と判断できます。
- llms.txt や AI 向け指示ファイルの検討:例えば「llms.txt」という、AIがサイトを巡回・参照しやすくするための指示ファイルの概念も出てきています。
- データの一貫性・エンティティの明確化:ブランド名、製品名、人物名、企業名などについて表記を統一し、混乱を生じさせないようにします。AI が「このエンティティは何であるか」を理解できるようにするためです。
3. 信頼性・専門性・引用可能性を高める
- 一次情報・専門的な情報を提供する:AI に参照されるには、他社サイトのキュレーションだけでなく、「このサイト/ブランドが専門的に解説している」という要素があると有利です。
- 被引用・言及の強化:従来の被リンク同様、他サイト・ニュース・論文・SNS での言及などが “エンティティの信頼性” を高める手がかりとなります。AI はウェブ上の多様な情報を学習基盤にしており、それらの指標も参照される可能性が高いと言われています。
- ブランド名・製品名の一貫性:ブランド・製品の表記ゆれ(例:「○○株式会社 製品」「○○製」など)があると、AI の参照精度が落ちる可能性があります。表記を統一しておくことが重要です。
4. モニタリング・指標の見直し
従来の SEO 指標(検索順位、オーガニックトラフィック、被リンク数など)だけでは十分ではなくなっています。LLMO では以下のような指標も検討対象です。
- AI による「ブランド名言及数」「回答中での自社言及率」
- AI 経由の流入やセッション数(可能な範囲で)
- ボットログ・AI クローラーのアクセス状況
- 誘導後の遷移・コンバージョン率(AI参照→自社サイトという流れ)
5. 組織・運用体制を見直す
LLMO に対応するためには、マーケティング/コンテンツ/SEO/テクニカルチームが連携して「AIに参照される可視性」を設計できる体制が望まれます。具体的には:
- コンテンツ制作時に「AIがこの情報を参照できるか」をチェックリスト化する。
- 技術担当が構造化データや指示ファイル(llms.txt 等)を整備する。
- SEO 担当が従来検索エンジンとの最適化と並行して「AI回答参照に備えた最適化」を行う。
- 分析/モニタリング担当が、AI経由流入や参照状況を追える仕組みを整える。
6. 将来展望:これからの LLMO に備える
ここ数年で予想される LLMO の進化・トレンドとして、以下のようなポイントが挙げられます。
- マルチモーダル対応:今後、テキストだけでなく画像・音声・動画を横断する LLM/生成 AI が増えるため、コンテンツもマルチモーダル最適化が求められるでしょう。
- リアルタイム・更新性の重視:AI が参照するデータソースが「リアルタイム/最新情報」を重視するようになれば、情報の鮮度・更新頻度も可視性に影響を及ぼす可能性があります。
- ナレッジグラフ・エンティティ強化の深化:「このブランド/この人物はこの領域の専門家である」というエンティティ信頼性が、AIの参照優位性を左右する時間が来るかもしれません。
- プライバシー・倫理・信頼の観点強化:AIが回答する際の出典・根拠がより透明になれば、不正確な引用・誤情報へのリスクも高まり、信頼できるソースとして認知されることがますます重要になります。
- 検索エンジン+生成 AI のハイブリッド化:AI が検索エンジンの機能を統合・進化させることで、SEO と LLMO の境界がさらに曖昧になる可能性があります。たとえば AI が検索エンジンのデータを基盤に回答を生成するようなモデルです。実際、先行記事では「GEO(Generative Engine Optimization)=LLMO は、SEO の延長線上であり、別物というわけではない」という指摘もあります。
- 指標・可視化ツールの発展:AI経由の可視性を測るためのツール・指標が整備されつつあります。これから数年で「AI参照数」「AI経由クリック」「回答中の引用率」などが一般的な KPI になる可能性があります。
LLMO に対応しないと起こり得るリスク
対応を怠った場合、以下のようなリスクが想定されます。
- AI の回答エンジンに参照・引用されず、ユーザーが生成 AI を使った際に自社が選択肢に上がらない。
- 従来の検索からの流入が減少傾向にある中、AI 経由での発見が増えているにもかかわらず無対応だと、全体の可視性が低下する。
- ブランド認知/信頼性の観点で、AI経由で他社が引用される中、自社が出ないことで「この分野の専門ではない」という印象を与えてしまう可能性。
- 長期的に「従来SEOだけを重視していた」企業が、AI新時代で遅れをとることで競争優位性を失う。
たとえば記事では、「この paradigm(枠組み)ではリンク構築やページ構成など、結局 SEO とほぼ同じ機構で見えるが、それでも AI 参照という点では“被リンク”ではなく“被引用”が重要になる」と整理されています。
まとめ:SEO と LLMO、両立してこそ強い
本稿を通じて整理したように、SEO と LLMO は別々のプロセスのように見えますが、実際には重なり合い、今後は“両立”が求められます。つまり、従来の検索エンジンで上位表示を狙う SEO 的な施策は依然として重要である一方で、生成 AI や LLM に「参照される/引用される」可視性を獲得するための LLMO 的な施策も同時並行で行うべきです。
特にこれからの時代、次のポイントを押さえておきましょう。
- キーワードや被リンクだけでなく、「ユーザーの質問に対して明確に答えているか」「AI が情報源として使いやすい構造になっているか」という観点を意識する。
- FAQ/Q&A形式、構造化データ実装、エンティティ(ブランド・人物・組織等)の明確化、AI向けサイト指示ファイル(llms.txt 等)の検討など、技術的・構造的な整備を進める。
- 従来の検索順位/オーガニック流入と並び、「AI経由の引用・参照」「生成 AI が出す回答に自社が含まれているか」「AI経由からの流入・遷移」をモニタリング指標として導入する。
- ブランドの信頼性・専門性を高めるために、一次情報・専門知見・被引用実績を積むとともに、エンティティとして AI が認識・参照しやすい体制を整える。
- 将来を見据えて、マルチモーダル対応、リアルタイム更新、ナレッジグラフ整備、検索+生成 AI のハイブリッド化といった潮流を視野に入れる。
SEO が「検索エンジンのルールに沿って可視性を獲得する」手法であるのに対して、LLMO は「生成 AI(LLM)に参照される・使われる可視性を獲得する」手法と言えます。どちらが「重要か」ではなく、どちらも「不可欠である」という視点が、これからのコンテンツ戦略/ウェブマーケティングには必要です。
今後、生成 AI がより私たちの日常的な情報探索手段になるにつれ、LLMO の重要性はさらに増すでしょう。だからこそ、今このタイミングで「SEO+LLMO」の両輪体制を整えておくことが、先行者として有利に立つためのカギになると私は考えます。